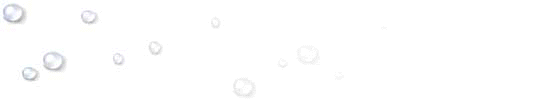
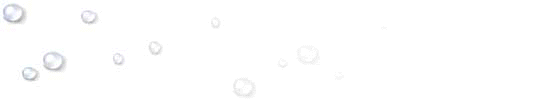
|
やねまで とんだ この村に到着したのは2日程前の事だった。 予定ではしばらく腰を落ち着けるつもりだった。 静かに時間が流れて行くあまりの長閑さに、早急に村を出ることを決めた。 長いことこの場所にいてはきっとこれ以上遠くに行くことが出来ないだろう。 失ったものの代わりを探してしまいそうだから。 村の教会の傍では子供達が集まって遊んでいた。 子供の何人かが小さなコップにストローを持ち、コップの中の液体をストローにつけて息を吹き込んでいる。 透明な七色の球体がひとつまたひとつと空を目指して飛んで行く。 ――マイクロトフは目を細めて、太陽の光を浴びるシャボン玉の行方を見送った。 *** 部屋はあらかじめ暗くしてあった。 人工の光は目に眩しいと彼が言うので、ベッドから少し離れたテーブルに小さなランプを置いてあるのみだった。 「カミュー」 軽くノックして入ったその部屋はいつも通りの風景で、カミューもまた普段と何ら変わらずベッドに横になっていた。 「カミュー、食事だ」 テーブルの上に夕食を乗せたトレイを置き、そっと毛布越しカミューに触れる。 カミューは起きていたようで、小さく「有難う」と呟くとこちらへ寝返りを打った。 「気分はどうだ?」 「いつも通りだよ」 頬の痩けた笑顔にマイクロトフも笑い返す。 食事を取らせる為に身体を起こしてやろうとすると、カミューの腕がそれをとどめた。 「カミュー、また食欲がないのか?」 「それもあるけれど……、マイクロトフ、お願いがある。明日は私も連れて行ってくれ」 「何だと?」 マイクロトフはあからさまに眉を寄せた。 カミューはマイクロトフの反応が分かっていたようで、微笑みでそれに応える。 「馬鹿なことを言うな。その身体で戦に耐えられる訳がないだろう」 「耐えきれるとは思っていないよ」 「……カミュー、お前」 「大丈夫……、犬死にするつもりはない。ただ、限界が来たんだ」 カミューは自ら上半身を起こそうとするが、細くなった腕が彼の体重を支え切れずにかくりと折れる。 マイクロトフはカミューに手を伸ばし、抱き締めるようにその身体を支えた。 「何が限界だと言うんだ……」 「……想いが。こうして眠り続けることも、身体が自由にならないことも苦ではない。でも私の想いは膨らみ過ぎた」 マイクロトフはカミューを見た。 美しく澄んだ琥珀の瞳は昔と変わらぬままだった。 「このまま病が進行すれば、私はいずれお前の事を忘れてしまうだろう。それは耐えられない」 「そうと決まった訳ではない。それにもしそんなことになっても、俺はずっとお前の傍にいるから大丈夫だ」 マイクロトフの言葉にカミューは黙って頷き、でもそういうことではないのだと目を閉じた。 「マイクロトフ。衰えて行くことに恐怖を覚えることはないか。」 「老いか」 「全てだよ。身体も心も想いもそうだ。肉体の衰えは受け入れた。心が頼り無くなってしまったことも仕方がないと思っている。だけど不思議だな、想いというものはとどまるところを知らない……随分、大きくなったよ。お前と出逢ったばかりの頃よりもずっと」 カミューは探るように腕をマイクロトフへ滑らせ、辿り着いたその手でマイクロトフの指に触れた。 「素晴らしい力だ」 カミューの細い指をマイクロトフも握り返した。 「だけどそれを楽しむことも限界に近付いた」 穏やかではあったが口調はしっかりとしていた。 「少し前から目が霞むようになった。……いずれお前の姿も見えなくなるのだろう。どうも眠る時間が長くなっている気がする……正直言うと夕べの事が夢なのか現実なのかはっきり区別がつかない」 「それが何だと言うんだ。眠る時間が増えたのは薬のせいだ。思考がはっきりしないのも当たり前だ。」 マイクロトフはそっと身体を離し、下から見上げる形でベッドの上のカミューを見た。 カミューの表情は相変わらず優しいままだった。 「記憶が曖昧になってきている」 外は少し風が強くなって来たようで、この時窓がガタリと揺れた。 身体は驚いても、マイクロトフは視線をカミューから外すことはなかった。 「いろんなことを少しずつ忘れて行く。今までの戦も旅もお前のことも。……怖くてたまらない」 すきま風が物悲しい音を立て、煽られたランプの炎が部屋の色を大きく揺らした。 「何もかも忘れて眠り続けるのは怖いよ」 「……カミュー」 「未だこの瞬間も、私の想いは強くなっているというのに」 「カミュー」 「失ったことにも気づかないくらいに一瞬で散ることができたら、どんなに幸せだろう」 「カミュー」 「今が限界なんだ」 「カミュー……」 「まだ私の身体が動くうちに」 「カミュー!」 カミューの手を強く握りしめたマイクロトフの、その骨張った指を静かに持ち上げて、カミューは愛おしそうに口唇を押し当てた。 「……私は失うなら一瞬がいい」 もう一度、口唇を押し当てる。 「少しずつ削り取られるなんて我慢できない」 もう一度。 「私の最期の我が儘を聞いて欲しい、マイクロトフ。」 マイクロトフは歪んだ表情のまま、美しい琥珀の瞳の中に鋭い光が灯るのを見上げた。 「私に生きるチャンスをくれないか。」 その痩せた腕で、身体でカミューはマイクロトフを見下ろした。 マイクロトフは射るような視線を正面から受けとめ、口唇をきつく噛み締めたが、やがて表情を緩めた。 笑顔は少し泣き顔にも似ていたが、マイクロトフは笑い返した。 「ずるいな、お前は……。さんざんお前に我が儘を言った俺が、お前の言うことを聞かない訳にいかないだろう。」 「マイクロトフ」 「無理だと思ったら引き返せ」 カミューの表情が輝いた。 「……ああ」 「無闇に前線に飛び込んだりするなよ」 「ああ」 「起き上がれないようなら連れていかない」 「ああ」 「馬も1人で乗れ。剣も自分で装備するんだ」 「……有難う、マイクロトフ」 マイクロトフは笑顔を消し、カミューに握られていた手で彼の指を掴み返した。 「礼など言うな。……謝罪もするな。精一杯生きろ」 「マイクロトフ……」 「俺のことなど考えなくていいから」 カミューは目を細めて、眩しそうにマイクロトフを微笑みながら見つめた。 それは端から見ると酷く儚気な笑みに見えたかもしれないが、マイクロトフもカミュー自身も強い力が溢れていたことは、重なった二人の手のひらの熱から充分分かり合えていた。 「忘れないよ、マイクロトフ」 忘れるくらいなら一瞬で消してみせる。 誰よりも何よりも、全てを失うその瞬間まで、たとえ失ったその後も。 お前への想いはとどまることを知らないから。 じわじわと奪われるくらいなら、共に散ってしまいたい。 私の最期の我が儘だ。 翌朝カミューの部屋を訪ねると、彼は一人で目を覚まし、防具を身につけていた。 その佇まいはいつか見た彼のシルエットと同じもので、マイクロトフは誤魔化しに笑うことしかできなかった。 愛剣ユーライアを腰に下げ、カミューはマイクロトフに両腕を伸ばした。 その細い腕に捕らえられ、力強く抱き合った。 しゃぼんだま とばそ 最早引き上げの合図を待つのみだった頃。 カミューの剣は確かだった。美しい剣の筋を造り出す、その見事さはかつての彼と同じ。 出陣前に馬に乗ることさえ手こずった、その姿が力強く剣を振るっていた。 それが大きく旗めいたのは、その頃だった。 翻るグレイのマントに赤い染みが浮かぶ。 紅が全身を染め始めて。 昔肩を並べたあの騎士団領で、戦場を駆け巡った彼の紅蓮の制服のような。 ユーライアが地上に落ちた。 スローモーションのようにゆったりとした時間の流れだった。 兵達が引き上げる中、抱き起こしたカミューは済まなさそうに笑っていた。 『ごめんね』 謝るなと言ったのに。 責めるようにそう言うと、咄嗟に出てしまったらしい謝罪にカミューは苦笑した。 何か言葉を紡ごうとして口を開けたが、それが音に変わる前に口唇は閉ざされてしまった。 *** 空はよく晴れている。 この分なら今出発しても、夜になる前に次の町まで辿り着けるだろう。 次は少し寒さの厳しい町がいい。 彼と過ごした懐かしい土地のような。 ――シャボン玉が空高く昇って行く。 眩しい光を反射して大きく膨らんだシャボン玉が、空を目指して弾けて行く。 カミュー、大丈夫だ。 俺はまだ泣くことができる。 ……だから、大丈夫だ。 やねまで とんだ やねまで とんで こわれて きえた |
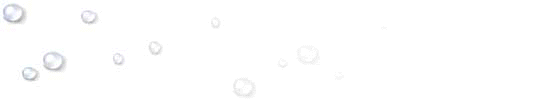
本日でサイト開設から半年が経ちました。
これまで遊びにきて下さった皆様に心から感謝しています。
これからも枠に捕われない、
自分の書きたいSSを書いていきたいと思っています。
今後とも当サイトをよろしくお願い致します。
