女帝誕生の謎
現代に生きる私たちは、西欧近世史における、ロシアのエカテリーナ女帝やイギリスのエリザベス女王、あるいはハプスブルグ帝国のマリア・テレージア女帝の華麗な活躍を知っています。そんなわけで、女帝の存在は、それほど珍しくないもののように思えます。
しかし、古代史における女帝は、大方の国において、例外的な存在であることが多いのです。息子の摂政を務める実質的な女王、というのは、けっこうどこにでもある話なのですが、自ら即位して帝王となる、ということはまれです。
たとえば中国。長い王朝史の中で、女帝はただ一人。7世紀末、唐の則天武后のみです。家父長制の発達した中国では、当然のことなのかもしれませんが。
しかし、兄妹婚がふつうであり、女性が皇位継承権をもっていたとされるエジプト古王国、中王国の王朝においても、女性の摂政や共同統治は多いのですが、ファラオとなる女性は例外でしかなく、その例外としてよく知られるのは、紀元前18世紀、第13王朝のハトシェプト女王のみです。
ひるがえって日本列島。6世紀末から8世紀後半にかけて、6人の女帝が確実に即位しています。このうちの皇極は斉明として、称徳は孝謙として、2度即位していますし、飛鳥、白鳳、天平、奈良と呼ばれるこの時代、女帝の時世の方が長いといえるのではないでしょうか。これは、世界史的に見て、かなり珍しいことです。日本初の女帝が誕生したのは、西暦593年のことです。
33代推古天皇、もとの名は豊御食炊屋姫(とよみけかしきやひめ)、若い頃には額田部皇女(ぬかたべのひめみこ)と呼ばれました。聖徳太子の叔母、といった方がわかりやすいでしょうか。
即位当時39歳といわれますが、これは数え年でしょうから、現代で言えば、37、8の熟女です。29代欽明天皇の皇女で、30代敏達天皇の皇后。すでに未亡人であり、数人の子持ちでした。日本書紀には「姿色端麗しく(みかおきらぎらしく)」と描写されていますので、美女だったとしておきましょう。
中国王朝、最初で最後の女帝、則天武后の即位が690年ですから、推古女帝の即位より100年ほど後のことです。
7世紀の東アジアは、女帝の世紀といえなくもありません。当時の朝鮮半島は、百済、高句麗、新羅の三国に分かれていましたが、そのうちの新羅の王朝でも、7世紀、善徳、真徳という二人の女王が、続いて即位しています。朝鮮半島初の女帝・善徳女王の即位は、632年ですから、推古女帝に遅れること40年です。
唐の則天武后にくらべ、新羅の2女王は、日本の場合に近いでしょう。
族内婚のなかった中国の王朝において、皇帝の後宮から成り上がって権力を握った則天武后は、当然、唐王室の李氏とは血筋がちがいます。彼女の即位は、王朝の簒奪を意味しますので、まさに例外なのです。
一方の新羅は、族内婚が主流で、この点、日本の王朝と共通していますが、2女王は王后として権力を握ったのではなく、独身の王女、王族として、その血筋による即位でした。
日本における女性の王者といえば、推古女帝の時代より350年ほど古い、邪馬台国の卑弥呼もそうなのですが、あえて数えておりません。卑弥呼は、3世紀、三国時代の中国、魏王朝に使いを出した倭の女王でして、中国側の記録・魏志に登場するのですが、日本側の記録に出てこないのです。
日本書紀では、神功皇后を卑弥呼と想定して、魏志倭人伝の記事を引用しています。しかし、「朝鮮征伐」の主人公であるこの神功皇后、戦後史学では伝説上の人物とされておりまして、朝鮮半島関係の記事に史実の反映があるにしても、4世紀後半の話であろう、とされております。つまり、卑弥呼より100年以上後のことなのです。
日本書紀によれば、神功皇后は、九州遠征中に夫である14代仲哀天皇を亡くし、幼い息子の応神天皇を15代として即位させ、摂政となりました。9代開化天皇の曾孫とされていまして、一応、皇族ということですし、皇后でもあったという筋書きです。
日本書紀が成立した720年当時、すでに、推古、皇極(斉明)、持統、元明と、4人もの女帝が即位していましたので、神功皇后が即位していたという話にしても不自然ではないのですが、なぜか、そうはなっておりません。皇族といえども天皇の曾孫では即位の条件として弱いか、とも思われますが、実在の皇極女帝は、30代敏達天皇の曾孫です。
実は、この皇極女帝をモデルに神功皇后伝説は創作されたのではないか、という説もあるのですが、それであればなおさら、なぜ神功皇后が即位したことにしなかったのでしょうか。神功皇后は創作された人物ではなく、なんらかの伝承に基づいて日本書紀は書かれていて、その伝承に神功皇后即位の事実がなかった、と考える方が自然ではないでしょうか。
神功皇后は女帝ではありませんでしたが、女性の王者とは、いえるかもしれません。応神天皇は幼く、母后である彼女が実権を握っていたという話だからです。
卑弥呼を女帝として数えなかったのは、その王者としての実体がどのようなものであったか、不明だからです。
中国史書の倭国記事は、伝聞によるものが多く、かなりいいかげんです。
聖徳太子が遣隋使を派遣したのは、推古女帝の時世。ところが隋書倭国伝では、倭国の王は男性だとされていて、摂政の聖徳太子か、あるいは大臣の蘇我馬子が、倭王を名乗ったのではないか、といわれています。
あるいはこれは、いいかげんであってあたりまえかもしれません。これほど情報量が増えた現代においても、諸外国の皇室報道には、唖然とするような誤解がたえません。他国の文化とは、それほどに理解しづらいものなのでしょう。
日本書紀、古事記の登場人物に、卑弥呼の投影を見る説も、ないではありません。神話時代の天照大神、あるいは10代崇神天皇の叔母・倭迹迹日百襲姫(やまととひももそひめ)あたりがあげられています。
それにしても、なぜ、推古女帝は即位したのでしょうか。これはいいかえれば、なぜ、聖徳太子は即位しなかったのか、という疑問にもつながります。
一つの焦点は、王権の正統性の問題です。唐の則天武后の場合はあきらかな簒奪で、彼女の死後、その時世は否定されますが、推古女帝は、皇女であり皇后であったという資格から、過去には例のない女性であっても、聖徳太子にまさって、皇位継承の正統性が承認され、以降、女帝が連続する契機となったわけです。
推古女帝の祖父、26代継体天皇は、15代応神天皇の5代孫と伝承されていますが、それが事実だとしても、その正統性には疑問符がつきます。
平安時代の話になりますが、鬼退治伝説で有名な武家の頭領・源頼光は、清和天皇の5代孫です。源頼光が皇位をねらえば、これは簒奪でしょう。継体は、王家の血は引くものの代を経た地方豪族だというのですから、後世の源氏や平家とかわらない存在です。
事実、継体朝には、九州で大規模な反乱が起こっています。朝鮮半島政策にかかわる反乱であったといわれますが、継体の正統性に疑問がなければ、規模は小さくてすんだことでしょう。
25代武烈天皇を最後に前王朝の正統な男系が絶え、継体は、王朝の後継者として迎えられたわけでして、その正統性を保証したのは、武烈の姉妹、手白髪皇女(たしらがのひめみこ)を皇后に迎えたことでした。即位以前からの正妻だったと思われる目子郎女(めこのいらつめ)との間に二人の男子があり、27代安閑、28代宣化として即位しますが、二人とも即位期間は短く、父と同じように、武烈、手白髪皇女の姉妹、つまり前王朝の皇女を后に迎えています。
そして、推古女帝の父である29代欽明天皇の即位となりますが、この欽明天皇は、継体と前王朝の皇女・手白髪皇女の間に生まれた息子です。しかも欽明の皇后石姫(いしひめ)は、異母兄の宣化が、前王朝皇女である皇后との間にもうけた娘でした。
つまり、継体朝となった時点で、母親、皇后の血筋が、皇位継承の条件として、クローズアップされたのです。
欽明崩御の後の跡継ぎは、すんなりと決まりました。欽明には多くの妃がいて、子供も多かったのですが、皇后石姫の息子、30代敏達天皇です。
推古女帝は、18歳にして、異母兄・敏達天皇の皇后となるのですが、推古の母は、大臣蘇我稲目の娘・堅塩姫(きたしひめ)です。
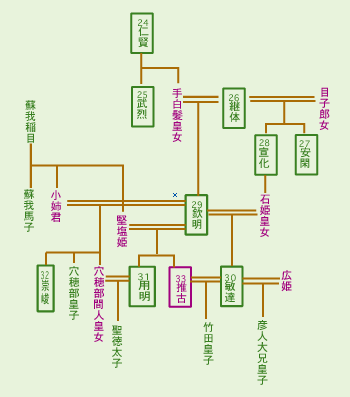
上の系図でおわかりいただけるかと思うのですが、欽明天皇の皇子女は、異母兄妹婚が多いのです。母方から前王朝の血を受けた欽明の血が尊ばれた結果でしょう。しかし、その欽明の正統な後継者、敏達天皇の崩御後、後継者選びは難航します。
推古女帝は敏達の後妻でした。先の皇后・広姫(ひろひめ)が薨去したため、後妻となったのです。広姫、推古ともに敏達の皇子を生んでいますが、年少のため、敏達の異母弟、つまり欽明の皇子たちが候補となります。皇后石姫腹には生存者がいなかったので、残る有力な皇子は、大臣・蘇我稲目の娘である堅塩姫、小姉君(こあねぎみ)姉妹の腹の皇子、ということになりました。
小姉君腹、穴穂部皇子(あなほべのみこ)は、敏達天皇の崩御直後、夫の葬送儀式に従う皇后推古を、犯そうとしたといいます。
このとき推古は数えの34歳。十分に色香のある年齢ですが、これを好色事件ととらえるのはどうでしょうか。
先例からして彼女は、先帝敏達の皇后として、後継者指名権を握っていたと考えられます。さらにいえば、欽明の皇女を皇后にたてることが、後継者としての有利な条件であったとも推測されます。推古さえ承知するならば、推古と結ばれることは、皇位継承への近道であったのではないでしょうか。
しかし、推古は承知しなかったようです。
彼女にとって、再婚は冒険です。事としだいによっては、先帝皇后としての権威、そして我が子の皇位継承権に、傷をつける恐れがあります。将来、幼い我が子、竹田皇子への皇位継承を願う推古にとって、とりあえずの後継者は、同母兄・用明が望ましかったのです。
古代の日本列島では、同母の兄妹は結婚できませんが、特殊な絆で結ばれていただろうということが、民俗学的に考察されています。柳田国男のいう「妹の力」です。これは近世まで、沖縄に色濃く残存し、琉球王朝における王族神女、聞得大君(きこえおおきみ)の存在にもつながりました。
倭の女王卑弥呼は、この姉妹の持つ霊能に基づいて生まれたと思われます。一族を統べる兄妹、あるいは弟姉の共同統治をヒメヒコ制といいますが、なんらかの理由でこのヒメの存在が大きくなり、卑弥呼は出現したわけです。
いえ、勘ぐれば推古は、穴穂部皇子を罠にはめようとしたのかもしれません。
用明は同母兄ですが、その皇后にたつ穴穂部間人皇女は、やがて推古の権威を脅かす可能性をもっています。穴穂部皇子は間人皇女の同母弟であり、下手に野心をもたれると、困る相手なのです。同母弟に傷をつけることは、間人皇女を牽制することでもあるでしょう。敏達崩御後の政局は、混迷していました。
これには、大陸における巨大帝国隋の誕生と、それにともなう朝鮮半島の波瀾が大きくかかわっているのですが、とりあえずここでは、崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏の確執が焦点です。
仏教が日本に伝わったのは欽明朝ですが、この外来宗教は、伝来当初、日本列島古来の神道との間に、摩擦を生じたのです。渡来氏族に影響力を持つ蘇我氏は、外来文化の受け入れに熱心で、崇仏派の中心でした。そのため、蘇我氏自身が渡来人ではないか、ともいわれてるのですが、これはどんなものでしょうか。この時期の渡来氏族は、後宮に娘を送り込む力をもっていなかったのですが、蘇我氏はそうではありません。伝承通り前王朝の外戚だった葛城氏の傍系で、母方に渡来人がいたと考えるのが自然でしょう。
蘇我稲目が欽明の後宮に二人の娘を入れ、蘇我の血を引く皇子女が多く生まれたことで、蘇我氏の力は大きなものとなります。その一人が推古なのですが、蘇我の血を引く初めての皇后となったことで、叔父の蘇我馬子の全面的な協力を得ることができました。馬子の動きを考えると、推古と用明の母・堅塩姫は馬子の同母姉であり、穴穂部皇子や崇峻の母・小姉君は、馬子とは異母だったのではないでしょうか。
敏達崩御から推古女帝誕生までの経緯を簡単に述べますと、まず推古を襲ったことを遠因にして、穴穂部皇子が殺されます。これは、推古と馬子が計ったことで、用明は黙認という形でした。
用明の皇后は、先にのべたように、穴穂部皇子の同母姉・穴穂部間人皇女ですが、聖徳太子の母である間人皇女は、まったく力を持っていなかったのです。
先帝の皇后を長年務め、同母妹として用明に影響力を持ち、実力者・馬子のバックアップを得ている推古が、すでにこの時点で、女帝に等しい力を行使していたといえます。
31代用明天皇は、しかし、2年ほどの在位で病のため崩御。後継者選びは混迷を極め、しかもその混迷の中で、崇仏派と排仏派の対立が激化します。もともと排仏派は、敏達と広姫の皇子・彦人大兄皇子(ひこひとおおえのみこ)を担ぐ気配を見せていたのですが、年少ゆえでしょうか、途中、穴穂部皇子を担ごうとしました。
彦人大兄皇子の最大の弱みは、母后・広姫を早くに亡くし、しかも、その後皇后にたった推古が、多大な力を握ったことでしょう。推古が皇女であったのにくらべ、広姫は王族にすぎませんでしたし、また有力な外戚を持ちませんでした。そして、推古にとっては、我が子の競争相手として、もっとも警戒すべきは、彦人大兄皇子だったのです。
用明崩御後の混迷は、蘇我、物部の戦争にまで至りますが、状況は排仏派の物部氏に不利で、大多数の皇子が蘇我に参戦した中で、彦人大兄皇子は静観します。結果、後継者は参戦した皇子の中から選ばれることとなり、32代崇峻天皇が誕生します。
推古はなぜ、穴穂部間人皇女と穴穂部皇子の同母弟である崇峻の即位を認めたのでしょうか。
穴穂部皇子の抹殺で、自信を深めていたのではないかと思われます。我が子の成長まで、崇峻をたてておいて、もしも崇峻に不穏な気配があれば抹殺という手がある、最初からそう思い定めていた気配があるのです。
崇峻天皇には、皇女の妃どころか王族の妃もなく、したがって皇后がいません。これは、先例から見て不自然なことですが、皇女が后となれば、年数がたつにつれ、推古の権威を脅かす存在となるのは見えていますし、ましてその后に皇子が生まれると、有力な皇位継承候補となります。推古にとって、望ましいことではないのです。まして崇峻は、用明のように同母兄ではなく、信頼する理由もなかったでしょう。
崇峻天皇は、5年ほどの在位の後、蘇我馬子の命で暗殺されます。直接手を下したのは、蘇我氏配下の渡来氏族、東漢直駒(やまとのあやのあたひこま)ですが、臣下が天皇を暗殺するという前代未聞の事件が起こったのです。
敏達崩御後、東アジア情勢の激動の中、内政外政ともに課題をかかえ、その矛盾が後継者争いを激化させたともいえるのですが、その中で、推古と馬子が主導権を握り続けました。しかし、天皇暗殺という荒技の後、成人前の推古の皇子を即位させることは、彦人大兄皇子の存在もあることですし、多大な反発をまねきかねません。しかも馬子にとって、彦人大兄皇子は、蘇我の血がまったく入らない赤の他人です。
そして、だれが後継者となったところで、推古の権威を脅かす存在となることは、わかりきっています。だとすれば、欽明皇女であり敏達皇后であった自分が即位すればいいのではないか、という推古の意志がまずあり、それを馬子が後押ししたのでしょう。そうすることによって、男系後継者問題は一時棚上げとなり、摩擦も少なくてすむはずです。
こうして、33代女帝推古は誕生しました。
摂政には、用明天皇と穴穂部間人皇后の長男・聖徳太子が据えられますが、これは、同母弟二人を殺された間人皇后への慰撫であり、馬子の意向だったでしょう。馬子は、聖徳太子の妃に、娘を入れています。また、あまり記録にあらわれないのですが、推古も娘の皇女を聖徳太子の妃としていて、おそらくこの皇女は、子をなすことなく、早くに亡くなったのでしょう。
推古の時世は36年の長きにおよびます。推古が後継者ともくろんだ竹田皇子は早世し、結果的にそうなったのですが、ではなぜ、聖徳太子が即位しなかったのでしょうか。
結局、聖徳太子の妃であった推古の娘の早世が、大きく影響したのではないでしょうか。娘が皇后になるのであれば、推古は聖徳太子の即位を認めたでしょう。
推古女帝については、蘇我馬子の操り人形のごとくいわれることが多いのですが、十分に権力の味を知り、それを楽しんだ女帝であったのではないでしょうか。
推古の次の女帝、皇極天皇は、舒明皇后ではありましたが皇女ではなく、敏達曾孫という遠い皇族です。この時代、推古の時世が長すぎたあまりに、皇子女が絶えたという特殊事情はあるのですが、先帝皇后としての権威が、即位の大きな条件であったことは確かでしょう。
皇極女帝は、きらびやかで、魅力的な女帝ですし、またの機会に、詳しく語れたらと思っています。
女帝はなぜ生まれたか。
男系相続者決定にともなう摩擦回避、というのも大きな理由ではありますが、皇位継承者指名権を持つ先帝皇后の権威と、日本古来のヒメヒコ制による皇女・皇族女の権威。その二つが、王朝の正統な男系断絶によって結びつき、高まっていたことは、特筆してよいかと思います。
最後に、人名は、わかりやすくするため、適宜、適当なものを使用しております。たとえば、「推古」という称号が後世に贈られたことは存じていますが、とりあえず使用いたしました。あしからず、ご了承下さい。