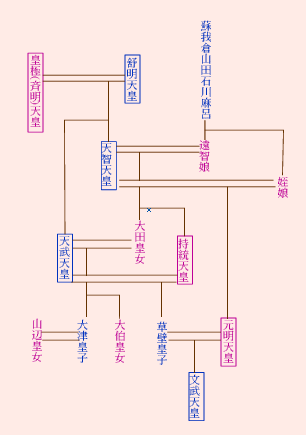かぐや姫幻想
貴公子たちの求婚も、帝の求愛でさえもふり捨て、月を見て憂える絶世の美女。
なよたけのかぐや姫を主人公とする竹取物語は、源氏物語の中で、「物語の出ではじめの祖(おや)」といわれています。
この竹取物語が、モデル小説だという説があるのをご存じでしょうか?
これは、ある特定の時代を風刺したものであり、かぐや姫に求婚する5人の貴公子たち、そして帝は、歴史上実在の人物をモデルにしたものだというのです。
じゃあ、かぐや姫にモデルはないのでしょうか?
今回は、そういうお話です。これについて、詳細な考証をいたしましたのは、江戸時代の国学者・加納諸平です。
物語の中の貴公子の名は、石つくりの御子(みこ)、くらもちの御子、右大臣あべのみむらじ、大納言大伴のみゆき、中納言石上のまろたり。そのモデルがだれであるのか、以下に列挙します。石つくりの御子
丹比真人島(たじひのまひとしま)
くらもちの御子
藤原朝臣不比等(ふじわらのあそみふひと)
右大臣あべのみむらじ
阿部朝臣御主人(あべのあそみみぬし)
大納言大伴のみゆき
大伴のすくね御行(おおとものすくねみゆき)中納言石上のまろたり
石上朝臣麻呂(いそのかみのあそみまろ)
すみません。「すくね」の文字がありませんでした。
下の三人は、歴然と名前が似ております。しかし、上の二人はまるでちがいますし、第一、物語では御子(みこ)、つまり皇子といいますか王子ですのに、当てられた人物は、臣下です。
これについて、まず、実在の丹比真人島ですが、父親は宣化天皇の孫で、王族であり、丹比王と呼ばれていたのです。丹比氏と石作氏は同族であり、臣籍降下以前の丹比真人島が、石作御子(いしつくりのみこ)と呼ばれていても不思議はない、といいます。
そして、藤原不比等ですが、後世史料の「公卿補任」などによりますと、天智天皇の落胤で、母親は車持国子君(くるまもちくにこぎみ)の娘・与志古娘(よしこのいらつめ)ということになっています。これは、藤原氏の潤色だといわれますが、平安時代には正式に認められ、公的な編纂物にかかれている話です。そういうわけで、母親の氏族名をとって車持御子(くるまもちのみこ)と呼べなくもなく、これならば、くらもちのみこに似ています。
それで、「公卿補任」を見てみますと、文武天皇の御代に、実際にこの5人が、重臣として名前を並べているのですね。「公卿補任」は後世史料ですけれども、日本書紀の持統朝末期にも5人の名前が並んでいて、文武朝の重臣であったことは、まちがいのないことです。
文武天皇は、持統女帝の孫にあたります。
持統女帝は、天智天皇の娘で、天武天皇の皇后。
天武崩御後、一人息子の草壁皇子(くさかべのみこ)を皇太子として、とりあえず自ら即位します。
ところが、ほどなく草壁皇子は薨去してしまいます。
天武天皇の皇子が多数いる中、持統女帝は、我が子草壁皇子の血にこだわり、草壁皇子が残した孫・軽皇子(かるのみこ)に皇位を譲り渡そうとします。
これは、当時としては異例なことでした。なにしろ草壁皇子は、即位しなかったのですから、軽皇子は天皇の子ではありませんし、天武天皇の皇子は数多いるのです。
なんとしても孫を即位させようとした女帝は、異例に異例を重ね、わずか15歳の軽皇子に皇位を譲ります。
こうして軽皇子は、文武天皇となりました。
そんなわけで、竹取物語の帝にもモデルはあるのです。文武天皇は、25歳の若さで崩御しますので、いかにも物語の登場人物にふさわしい、うら若き帝です。
それで、かぐや姫はいったい誰なのか?
その疑問に取り組む前に、竹取物語をモデル小説と断言するには、ちょっと問題があります。
まず竹取物語は、その文体などからいって、平安時代に書かれたことが推測されます。
文武朝といえば、西暦697年から707年。藤原京の時代です。この民話風の物語に、200年も前の人物をモデルにする必要があるのでしょうか?
ここで浮上してくるのが、竹取物語には漢文の原作があった、という説なのです。
漢文の物語ならば、もっと文武朝に近い時代に書かれてもおかしくないですし、また、竹取物語の文体には、漢文をもとにしたらしい形跡が見てとれるのだそうです。
が、しかし、その漢文の原作とは、日本で書かれたものではなく、中国の小説だったのではないか、という説もあります。つまり、竹取物語は翻訳小説だという説なのですが、近年、その有力な証拠として、1961年に上海で刊行されたチベット自治州の民間説話集から、『斑竹姑娘』があげられました。
この斑竹姑娘の筋を簡単にのべますと、貧しい母子家庭の男の子が、強欲な領主が竹を伐るのを嘆いていましたところ、竹に涙がかかって、その竹からかわいい女の子が生まれます。男の子はその女の子を愛するようになるのですが、美しく成長した女の子に5人の求愛者が現れ、女の子はそれを退けるために、それぞれに難題を出します。5人はみな失敗して、結局女の子は、最初に自分を見つけてくれた男の子と結婚する、というハッピーエンド物語なのです。
そして、5人の求愛者たちに与えられた課題と、その成り行き、結果が、たしかにとてもよく、竹取物語に似ているのです。
しかし、だからといって、千年以上も前に書かれた竹取物語と現代に採話された斑竹姑娘に、共通の原典小説があったはずだと推測するのは、飛躍にすぎるでしょう。
竹取物語には、もちろん説話的な要素がありますし、古代の日本とチベット自治州に、似た説話があったとしても、おかしくはありませんし、説話の伝搬は、当然、あるでしょう。
チベットといっても、この説話が採取されたのは四川省西北部で、いわゆる照葉樹林帯なんです。湿潤、温暖で、椿や楠など、つやつやとした葉をもつ植物が茂る地帯が、西はこのチベットのあたりから、東は朝鮮半島南部、そして西日本一帯までひろがっているのですが、これを照葉樹林帯といい、そこに住む民族には、共通の文化的要素があるといわれています。
細部の類似についていえば、斑竹姑娘の記述に、採話者の予断がはさまれた可能性もありますし、これはむしろ、近代日本で多数刊行された竹取物語の近代中国への伝搬を、考えた方が自然でしょう。
近代中国の文学者は、大多数が日本留学をしていますし、中国大陸へ竹取物語が持ち込まれた可能性は、十分にあります。
竹取物語と斑竹姑娘をくらべてみると、千年の命を保った竹取物語の魅力が、むしろ鮮明になります。
領主の専横を憎む貧しい青年が幸せになるという、登場人物の身分的な設定からいえば、斑竹姑娘は竹取物語よりも、はるかに近代的です。しかし、いかにも民話的なハッピーエンドは古風で、訴えるものを持ちません。
竹取物語の最大の魅力は、かぐや姫が異世界に属する存在であり、栄耀栄華も恩愛も、かぐや姫をこの地上へつなぎ留めることはできず、ついに月の世界、異世界へ帰ってしまうという設定にあります。
愛憎渦巻く現世を厭って出家する、源氏物語の女性たちの哀感。それは、かぐや姫の心象風景の後裔ですし、そして、この現代でさえも、月を見上げて嘆くかぐや姫の姿は、リアリティを持ち得るでしょう。
「私はこの世界では異質だ」「私が本来属する場所はどこか別の場所にある。それは幻のユートピアかもしれないけれど」というような思いは、現代の私たちにも身近なものです。
小野不由実の十二国記番外編『魔性の子』は、そういう現代的な心情描写で異世界にリアリティをもたせたファンタジック・ホラーですが、これは、かぐや姫の現代的な心象風景でもあるでしょう。
竹取物語はやはり、紫式部が「物語の出ではじめの祖」と述べたにふさわしい物語なのです。
その竹取物語が、文武朝の人物をモデルにしているのであれば、かぐや姫の哀感もまた、なにか、その時代の哀感をもとに想起され、記されたものであろうと思われます。
というわけで、かぐや姫のモデルとしては、私の知るかぎり、二つの説があります。双方、ある特定の人物というわけではなく、一つは采女(うねめ)説、もう一つは斎宮(いつきのみや)説で、どちらも、朝廷の神事にかかわりのある女性たちです。
竹取の翁、つまりかぐや姫の育ての親は、「さかきのみやつこ」と呼ばれます。榊(さかき)は、現在でも神事にかかせない神木ですが、伝書本によっては、「さぬきのみやつこ」ともなっていて、これは漢字で書けば「讃岐造」。平安時代の資料では、讃岐には忌部(いんべ)氏が住んでいて、毎年、朝廷に竹を献上していたのだそうです。したがって、讃岐造は忌部氏であったとも考えられます。
忌部氏といえば、中臣(なかとみ)氏とともに朝廷の神事を司った氏族ですが、次第に中臣氏に押され、平安時代には中枢から退けられます。
ところで、くらもちのみこのモデルといわれる藤原不比等(ふじわらのふひと)は、天智天皇の落胤といわれますが、大化改新の主、中臣鎌足(なかとみのかまたり)の息子でして、もともとは中臣史(なかとみのふひと)と呼ばれました。持統朝において、藤原と名乗るようになったのです。
ともかく、奈良県広陵町には、讃岐神社という古い神社がありまして、竹取翁、讃岐造の住まいだった場所と伝承されています。藤原京から、ほど遠くない場所です。
また、かぐや姫の名付け親は、三室戸の斎部(忌部)のあきたであり、これは三輪の忌部氏です。
いわばかぐや姫は、神官に育てられたわけでして、采女、斎宮が持ち出されるのは、妥当な推測です。
かぐや姫采女説は、梅山秀幸氏の『かぐや姫の光と影』(人文書院)で述べられているのですが、文武帝の後宮の藤原氏支配、大宝律令による采女の身分規定から、文武朝の采女たちの悲哀を推測しています。
采女というのは、そもそもは、地方豪族が服属の証に朝廷に差し出した女性たちであるといわれ、帝を中心とする神事に奉仕しますので、権威ある存在だったわけです。また、帝の手がつくことも多く、天武天皇までは、多数の采女腹の皇子女があります。
しかし、律令制が整い、神事と政治に明確な区分がついてきますと、采女はただの下級女官となります。その転落の画期が、文武朝だったというわけです。
先に、文武天皇の即位は、伝統に逆らい、無理に無理を重ねたものだと述べましたが、持統女帝に協力して、それを推進したのは、藤原不比等であろうといわれます。
近年では、記紀神話の天孫降臨は、持統女帝から孫の文武天皇へ、皇位が受け渡される正統性を保証するため、藤原不比等によって構成、創作されたものだとするような、極端な説も主張されております。
そのことの真偽はともかく、それほどに文武即位は異例であり、文武帝の後宮も異常でした。
これまでの例からして、皇女、皇族女が一人は妃となり、皇后となるべきところ、一人としておりません。
後宮に入ったのは、藤原氏、石川氏(蘇我氏)、紀氏という重臣の娘たち。このうち、石川氏と紀氏の娘は、後に身分を落とされ、石川氏腹の皇子たちは臣籍降下させられてしまっております。
これはあきらかに、娘の宮子を後宮に入れた、藤原不比等の陰謀でしょう。
宮子が文武帝との間にもうけた一粒種の首皇子(おびとのみこ)は、これも無理に無理を重ねて、やがて聖武天皇として即位します。聖武天皇は、奈良の大仏を造ったことで有名です。
つまり文武後宮の宮子入内は、藤原氏が後宮を独占し、藤が松にまきついて花を咲かせるように栄えた、その最初の一石だったわけです。
藤原不比等が完成させた律令制の大枠は、結局、明治維新まで存続しますし、皇后は皇族か藤原氏からという伝統にいたっては、多少の例外はありますが、なんと戦前まで尾を引きました。
明治天皇、大正天皇の皇后は藤原氏ですし、昭和天皇の皇后は皇族でおられました。今上帝にいたって、初めてその伝統は破られたのです。
梅山氏は、このような藤原不比等の文武後宮対策から、大規模な采女たちへの迫害があった、とされるのですが、これは、果たしてどうでしょうか。文武帝に、采女腹の皇子があったとしても、それは、藤原氏の血を引く首皇子の競争相手として、正統性に欠けます。文武帝が采女に手をつけたところで、たいした問題とはならないはずです。
梅山氏の説からすれば、かぐや姫のモデルとしてふさわしいのは、むしろ、皇族女性でしょう。
文武帝には、ほんとうに、皇后となる皇族の妃がいなかったのでしょうか。
これは、だれしも抱く疑問でして、梅原猛氏は『黄泉の王(よみのおおきみ)』において、文武帝の皇后でありながら、藤原不比等に抹殺された皇女がいたのではないかと、推察されています。
天武皇女で蘇我赤兄の娘を母とする、紀皇女(きのひめみこ)です。
当時の皇女の中で、このお方だけ、死期が正史に記されてないこと、そして万葉集に、次の歌が収録されていることからの推測です。
軽の池のうら廻み行き廻る鴨すらに
玉藻のうへに独り宿(ね)なくに
「軽の池を泳ぎまわってる鴨だって、一人じゃ寝ないわよ。なんで私が、男と寝ちゃいけないのさ」
なんとも、すさまじいお歌です。
文武帝は、軽皇子と呼ばれましたので、軽の池は文武後宮であり、自分をそこに囲われてしまった鴨に例えているととれます。
もう一つ、紀皇女のものと伝えられる歌が万葉集にありますが、これがまた、よけいすさまじいものです。
おのれゆゑ罵らえて居ればあを馬の
面高夫駄に乗りて来べしや
「あんたのおかげで、罵られてるんじゃないのさ。その最中に、なにをえらそうな顔で、馬に乗ってくるのさ」
この「あんた」がだれなのかは、ちょっと問題があってわからないのですが、私には、文武帝その人ではないかと思えます。
紀皇女は、天武晩年の皇女と考えられますが、そうであっても、文武帝よりは数歳年上でしょう。
もし、梅原氏の推測があたっていたとすれば、年下の甥の妃とされた紀皇女は、不自由さにうんざりしていたということになります。
文武帝を溺愛する、文武帝祖母の持統女帝と、文武帝の母で後に元明女帝となる阿閉皇女。
……ばばあどものおかげで、こういうことになっちまったけど、おもしろくもないガキのために、ああだこうだと不自由で、おまけに、どうも不比等とできてるらしい橘三千代(藤原不比等の妻で高級女官)が、陰険に見張ってるじゃないのさ。
私は別に、皇后にも女帝にも、なりたいわけじゃないわさ。
だいたい、えらそうなばばあどもが、皇子でもないガキを即位させるなんて、常識はずれの無茶のあげく、がんばってたんじゃあ、私は単なるお飾りじゃないのさ。
ふふん、私がどの皇子の子を孕もうと、表面はばばあどものガキの子だわよ? だいたい、ばばあたちだって、ちゃんと亭主の子を孕んだって証拠はないわよ?
まあ、あれね、天智帝の落とし種だなんていってるけど、結局、不比等は成り上がり。成り上がりの血が入るくらいなら、天武の娘である私が、異母兄の子を産めば、はるかに高貴だわよ?
……と、まあ、紀皇女は、そのくらいのことを考えていたのではないかと思えるほど、奔放で、情緒のかけらもないお方です。
紀皇女を慕っていた男性については、一人だけ、はっきりと名がわかっております。やはり万葉集に歌を残しておりまして、文武3年に若くして薨じた弓削皇子(ゆげのみこ)です。
吾妹児(わぎもこ)に恋つつあらずは
秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを
これが、紀皇女を思った歌なのですが、いやはやなんとも、恋する男は、ロマンチストです。
弓削皇子は、天武皇子で母は天智皇女という、皇位継承者として文句のない皇子です。文武帝即位に異議をはさもうとしたという記録があり、正史にはあらわれませんが、謀殺された可能性も高いのです。
結局、文武帝の後宮は、藤原宮子の独占状態となったわけですが、宮子は繊細な女性であったらしく、首皇子出産の直後、精神を患い、人前に姿を現さず引きこもる生活を、晩年まで続けます。
父・不比等の無理押しから、わが身によせてくる周囲の白眼視に、宮子はたえられなかったのでしょう。
それほどに、文武後宮は、異常な場所であったのです。
なるほど、紀皇女が文武妃であったとすれば、かぐや姫のモデルとしてふさわしいかもしれない、とも思わせるのですが、この奔放さは、どうでしょうか。だれでもおいで、といわんばかりの歌は、けっして現世を全否定するものではないでしょう。
かぐや姫のイメージは、やはり、冷たく男を拒否する、高貴で神秘的な処女、ではないでしょうか。
それに、問題となるのは、かぐや姫に求婚する5人の中に、藤原不比等がいることです。娘の競争相手として、冷徹に抹殺しただろう相手に、望みのない求婚をするというのも変な設定です。
そこで浮かび上がってくるのが、斎宮(いつきのみや)説です。
斎宮とは、伊勢で、天皇の分身として皇祖・天照大神の御魂代(みたましろ)となる皇女、つまり皇族神女です。
斎宮在任中に、性的交渉は許されません。たとえ天皇といえども手を触れることのできない、聖なる女性といえるでしょう。
斎宮制がはっきりと制度化されたのは、ちょうどこのころからでして、実際に伊勢にいたことが確実とされる斎宮は、天武朝の大伯皇女(おおくのひめみこ)だともいわれます。
つまり斎宮制は、いってみれば律令制と平行して整備されたものなのですが、もちろん、なにもないところから突然、斎宮が現れたわけではなく、それ以前から、斎宮の伝承は長くあります。
斎宮とは、かつてのヒメヒコ制のヒメであり、もともとは皇女ではなく皇妹であっただろうことを、詳細に考察しているのは、倉塚曄子氏の「巫女の文化」です。
皇家の支配がひろまる段階で、服属した豪族が皇家に差し出したヒメが采女であり、皇家の祖神・天照大神が、他氏族の上に君臨するために宮中を出て、ヒメもまたそれにしたがい、皇権の中枢を離れ、皇家は妹の霊能という神話的なものと決別したのだというのです。
これは簡単にいってしまえば、かつてのヒメの栄光は、祭事と政治の分離が進むにつれ、皇后に肩代わりされ、女帝の出現となり、ヒメは辺境へと追いやられた、ということになるでしょう。
実際、天武朝の斎宮・大伯皇女は、追いやられた、といっても過言ではないでしょう。
天武天皇には、数多の皇子女がおりましたが、皇后持統には草壁皇子一人しかなく、そのもっとも手強い競争相手は、持統の同母姉・大田皇女(おおたのひめみこ)の忘れ形見である大津皇子(おおつのみこ)であり、大伯皇女は、その同母姉だったのです。
大田皇女は、天武即位前に世を去っていたのですが、もし生きていたならば、持統の同母の姉なのですから、持統ではなく大田皇女が、皇后になっていた可能性が高いのです。大伯皇女の結婚相手によっては、大伯皇女の権威が無視できなくなる可能性がありますし、それによって同母弟の大津皇子も、力を得るでしょう。
だからこそ、大伯皇女は、13歳で伊勢歳宮となり、飛鳥を離れなければならなかったのであり、そこには、我が子草壁皇子の安泰を願う、皇后持統の意志が働いていたでしょう。
そして、古事記に描かれた初代伊勢斎宮・倭姫(やまとひめ)は、天皇ではなく、王位継承の争いに敗れ、王権から遠ざけられた政治的敗者の守護者です。
記紀伝承最大の英雄、倭健命(やまとたけるのみこと)は、古事記において、伊勢斎宮であり叔母である倭姫に、「天皇既に吾を死ねと思ほせか」という嘆きの言葉をもらします。
父である天皇によって、辺地への征服戦争の指揮を命じられ、各地を転戦しながら、報われることがない。敢然と戦いに勝利しながら、しかし、自分は父に憎まれているのではないかと、苦い思いがわく。
「おとうさんは、私が死ねばよいと思っているのだろうか」というその一言が、古代の英雄像に、近代的で、普遍的な魅力をそえているのですが、現代的な感覚からいえば、この吐露は、母親か、あるいは恋人になされるものでしょう。
妹の霊能を代行する叔母、王権から疎外されたヒメ。それは、古代において、母よりも恋人よりも、英雄の嘆きを受け止めるにふさわしい人物だったのです。
倭(やまと)は国のまほろば
たたなづく青垣
山隠れる 倭し美し
倭健命が死を目前にして歌う国偲歌(くにしのひうた)が美しく、哀切なのは、倭姫に内面を吐露していればこそです。
嬢子(をとめ)の床の辺に
吾が置きし つるぎの大刀(たち)
その大刀はや
剣を置いてきたのは、恋人・美夜受姫(みやずひめ)のもとです。
しかし、死の直前に倭健命の脳裏に浮かんだのは、その草薙の剣を自分に与えてくれた、倭姫の姿だったでしょう。
かぐや姫斎宮説は、上井久義氏の「日本古代の親族と祭祀」に出てくるものです。上井氏は、かぐや姫を平安時代の物語としてあつかっていますので、伊勢の斎宮御所が多気にあることから、これは竹の都だといいます。そして、畿内に移住した隼人たちが斎宮の行事のために、竹細工を献上していることや、隼人たちの故郷、鹿児島県加世田市が竹林の里であったことなどから、かぐや姫の説話的な部分を、隼人たちの伝承であるというのです。
これはこれで、なかなかに説得力のある説なのですが、モデル小説であることと、かならずしも矛盾するものではないでしょう。
だとすれば、実在の斎宮個人に、かぐや姫のモデルをみてみるのも、一興ではないでしょうか。
さて、天武天皇の斎宮として大伯皇女が立ったあと、持統女帝は、斎宮を立てなかったのです。このことには、後でまたふれますが、大伯皇女の後は、問題の文武朝に、3人の斎宮が立っています。
平安時代の斎宮は、天皇崩御、あるいは退位の場合のほか、斎宮個人の親族の喪で退くこともあるのですが、文武朝の斎宮が、なぜ交代したのか、理由はわかりません。
しかし、それよりなにより、文武朝の3人の斎宮は、天智・天武の皇女なのですが、3人が3人とも、斎宮を退いた後、平穏無事に長生きをして、そのうちの二人は、皇族と結婚して子供までもうけているのです。つまり、かぐや姫のモデルとしては、悲劇の影に欠けるではありませんか。
となれば、これはもう、大伯皇女と考えるしかありません。
大伯皇女は、大宝元年(701年)、つまり、文武帝が即位して4年後に、40歳で世を去っています。文武帝より20も年上であり、少年帝の憧れの人としては、少々年がいきすぎているのですが、斎宮であるということは、特別なことらしいのです。少女のうちに斎宮となった場合、月事がないままに過ぎる、という話もあります。
それはさておき、少年帝だからこそ、年上の女性に憧れるということもあるでしょう。15歳の少年が30代半ばの女性に恋をしても、それほどおかしくはないでしょう。
そしてなにより、これは物語のモデルの話なのですから、それほど厳密に年齢を考える必要もないでしょう。
そうなのです。大伯皇女は、悲劇の斎宮です。
早くに母親である大田皇女を失い、たった一人の同母弟である大津皇子とも別れ、13歳にして伊勢に旅立ち、そして14年の後、帰り着いた飛鳥の都に、愛する弟の姿はありませんでした。
大津皇子は、正史である日本書紀が「たくましく、学才があり、弁舌、詩文にもすぐれ、父の天武天皇に愛されていた」と記しているほどで、血筋の上からも文句のない、皇位継承候補でした。あるいは天武帝は、大津皇子に位を譲る気になっていたのではないかと、推測までされているほどです。
しかし、もしそうだったとすれば、天武帝は、妻の持統皇后を甘く見ていました。天武崩御と同時に、持統皇后は政権を握り、大津皇子に謀反の罪をきせ、処刑したのです。
危機が身に迫るのを感じた大津皇子は、一夜、伊勢の大伯皇女のもとを訪れたことが、万葉集によって知れます。吾が背子(せこ)を大和へ遣るとさ夜ふけて
暁露に吾が立ち濡れし
二人行けど行き過ぎがたき秋山を
いかにか君がひとり越えなむ
「大和へ帰らなければならない愛しい弟を見送り、立ちつくしている間に夜はふけ、暁の露に濡れてしまいました」
「二人でいってもいくことの辛いこの秋の山道を、どうやってあなたが一人、こえていくのでしょう」
このころすでに、草薙剣は尾張にあったようです。かつての倭姫のように、王権の守り刀を与えてやることもできず、斎宮は無力に弟を見送ります。王権にまつわる姉妹の霊能の、落日の姿でした。
そして、その年の暮れ、斎宮の任が解けたのは、愛しい弟の刑死によってでした。
神風の伊勢の国にもあらましを
なにしか来けむ君あらなくに
うつそみの人なる吾や
明日よりは二上山を兄弟(いろせ)とわが見む
磯の上に生ふる馬酔木(あしび)を手折らめど
見すべき君が在りといはなくに
「あのまま、伊勢の国にいればよかった。あなたのいない飛鳥へ帰ってもなにがあるというのでしょう」
「現世に生きるしかない私は、あなたの遺骸の眠る二上山を、あなたそのものだと思って、せめてのなぐさめとしましょう」
「磯(石の多い場所)の上にはえている馬酔木の花を手折ってみようと思っても、きれいでしょう、と見せるあなたはもういないのです」
大伯皇女の万葉歌は、まさに絶唱で、できすぎの感じさえしますので、万葉集編纂以前に、この姉弟の歌物語が創作されていたのではないか、という説さえあります。日本書紀によれば、大津皇子処刑のとき、妃の山辺皇女(やまべのひめみこ)は、髪をみだしてかけつけ、ともに死んだといいます。もっともこの表現は、後漢書にならったものだそうですので、実際には、人々がそういう場面を目撃したわけではありません。
しかし、それにしても人々は、若くして謀殺された大津皇子に、かぎりない同情をよせたことでしょう。そして、その姉であり、清らかな斎宮でもあった、大伯皇女にも。
大津皇子の死のころから、天変地異や天候不順が続きました。同情は畏れともなり、持統女帝への非難の眼差しともなったでしょう。
そして、そうしてまで女帝が即位させたかった我が子・草壁皇子は、ほどなく病で世を去ったのです。
大津皇子の遺骸は、二上山に改葬され、最初に埋められていた場所は、薬師寺境内に取り込まれました。
大伯皇女は、持統と天武の寺である薬師寺に、参ったことがあったでしょうか。
いいえ、参りはしなかったでしょう。
大伯皇女をささえていたのは、元斎宮としての誇りのみであり、それだけが、彼女が女帝につきつけることのできた刃だったはずです。
仏法の慰めは、彼女には不要のものでした。
律令制から疎外されようとしていた旧勢力の中には、そんな大伯皇女の姿に賞賛の声もあったでしょうし、それはそのまま、持統女帝への無言の非難ともなったでしょう。
女帝は、自ら斎宮をかねているともいえるので、斎宮を派遣しなかった、という説があります。
しかし、最初の女帝である推古のときにも斎宮がいたという伝承がありますし、元正女帝のときには、あきらかに斎宮派遣が正史に見えます。斎宮を立てなかったと、はっきわかっているのは、持統女帝のみなのです。
持統女帝が斎宮を立てなかったのは、前斎宮・大伯皇女への対抗意識があったからではないでしょうか。
皇祖・天照大神の分身は私であり、だから私の子が即位することはあたりまえ。大津を殺したことも、非難されるいわれはないよ、と。
後世、天皇が伊勢へ出向くことはタブーとなったようでして、伊勢の地を踏んだ天皇は、ほとんどいません。
しかし持統女帝は、伊勢を訪れました。それも、重臣の反対を押し切って、です。
諫言した重臣の名は、三輪朝臣武市麻呂。しかもこの諫言は、女帝の逆鱗に触れ、武市麻呂は失脚しました。
三輪氏は古い家柄で、そもそもは神祭りにもかかわりのあった一族です。かぐや姫の名付け親である三室戸の斎部を思い起こさせます。
輝ける日の御子(みこ)であったはずの弟は、月読命(つくよみのみこと)となって、落日の二上山に眠る。それでは、日の女神の分身であった私も、月世界の住人となろう……。
大伯皇女は、どこに住んだのでしょうか?
竹取翁、讃岐造の住まいだったといわれる讃岐神社のあたりは、二上山を目前にしています。斎宮であったとき、配下にいた忌部氏の世話で、大伯皇女がこのあたりに住んだことを想像するのも、それほど突飛ではないでしょう。
竹の里のかぐや姫の物語は、千年の時を越え、古代史の幻想の霧の中へと、私たちを誘うのです。