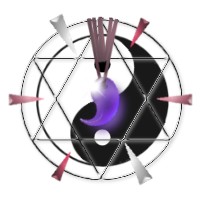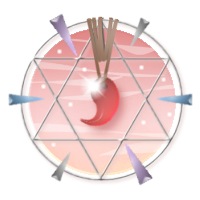ギリシャ・ローマ神話と日本神話に、驚くほどそっくりなエピソードがあることを、ご存じでしょうか。
今回は、なぜ、はるかに遠い西と東に、そっくりな神話が存在するのか、その謎を追ってみました。
「そっくり」と述べましたが、いったいどれほど似ているのか、たとえば黄泉の国のお話。
日本神話の女神イザナミは、火の神を出産したことにより、死んでしまいます。
兄であり夫であったイザナギは嘆き悲しみ、どうしてもあきらめきれず、妻をつれもどすため、黄泉の国へと下ります。しかしイザナミは、すでに黄泉の国の食物を食べていたため、地上に帰ることは、黄泉の国の掟に反します。
「黄泉の神々と相談しますので、待ってください。その間、決して私をみないでくださいね」とイザナミは訴えるのですが、あまりに長く待たされるので、イザナギはのぞき見してしまいます。
ところが、のぞき見たイザナミは腐った死体そのままで、蛆がわき、その身体から8人の雷神が生まれ出て番をしています。
あまりの恐ろしさにイザナギは逃げだし、それに気づいたイザナミは怒って、鬼や雷神においかけさせます。みな失敗するのを見て、ついにはイザナミ自身が追いかけるのですが、イザナギは無事地上に帰り、二人の中は完全に決裂します。
黄泉の女王となったイザナミは、「私はあなたの国の人たちを一日1000人ずつ殺しますから」と宣言し、イザナギは、「だったら私は、一日1500人の子どもが生まれるようにしてみせる」と返します。
国産みから人の子の生と死を語る神話の一環ですが、またこれは、愛し合っていた夫婦神の離別のお話でもあります。
この黄泉の国神話とギリシャ・ローマ神話との最初の共通点は、冥界での食の禁忌です。
冥界の王プルトン(ハーデス)は、大地の女神デメテル(ケレス)の娘・ペルセポネ(ポロセルピナ)に恋をして、冥界に連れ去ります。デメテルの嘆きに大地は荒れ、訴えを受けたゼウスは、「ペルセポネが冥界でなにも食べていなければ地上に帰ってもいい」と裁定を下しますが、すでにペルセポネは、ザクロの実を食べていました。
そんなわけで、結局ペルセポネは、一年の半分を大地の女神として母と共に地上で過ごし、半分を夫と共に冥界の女王として過ごすこととなったのです。
ペルセポネとイザナミは、大地の女神が、冥界の食べ物を口にしたため地上に帰ることができず、冥界の女王となったという、けっして、偶然とは思えない共通点を持っているわけです。
さらに、アポロンの息子・オルフェウスとニンペのエウリディケのお話も、イザナミ・イザナギ神話と似ています。
オルフェウスの愛妻・エウリディケは、新婚間もなく、蛇に足を噛まれて死にます。オルフェウスは冥界へと下り、冥界の王と女王、プルトンとペルセポネの前で、得意の竪琴を奏で、「愛する妻を返してください」と歌います。その歌声にこめられた悲しみに、プルトンもペルセポネもうたれて、承諾します。
ただし、条件がありました。地上に帰りつくまで、オルフェウスは、けっしてふり返って妻を見てはならない、というのです。地上に近づいたところで、ついオルフェウスはふり返り、エウリディケが地上に帰ることは許されませんでした。
「見るな」という禁忌により冥界からの妻の蘇りが不可能になる、という相似は、これまた、偶然と言うにはできすぎでしょう。
さて次は、日本神話の八俣の大蛇(ヤマタノオロチ)のお話と、ギリシャ・ローマ神話の海の怪物のお話です。
イザナギとイザナミの息子、スサノオは、父から「海をおさめよ」と命じられますが、黄泉の国の母・イザナミを慕って、父には従いません。結局、姉のアマテラスがおさめる天界で乱暴を働き、地上に追放されます。
降ったところは出雲の国で、大きな川を上流にさかのぼると、出雲の国の神の夫婦が、美しい娘クシナダ姫を真ん中にして、泣いています。スサノオがわけを聞いたところ、八俣の大蛇という怪物の生け贄に、クシナダ姫を差し出さなければいけないというのです。
スサノオは怪物を退治し、クシナダ姫と結婚して出雲の王となるのですが、これが、ゼウスの息子・ペルセウスの冒険にそっくりなのです。
翼のついた靴を履いた英雄ペルセウスが、エチオピアを上空を通りかかったところ、海岸の岩に美しい乙女が鎖でつながれています。
ペルセウスが乙女にわけを訪ねたところ、乙女は、エチオピア王の娘・アンドロメダで、海岸を荒らす海の怪物に、生け贄とされるのだというのです。
ペルセウスは怪物を退治し、アンドロメダと結婚してエチオピアの王となります。
ところでスサノオは、クシナダ姫との間に多くの子孫を残して、結局、母のおさめる黄泉の国へと下り、冥界の王となります。冥界の宮殿では、娘のスセリ姫と二人で暮らしていました。
一方、地上の出雲では、スサノオの子孫にあたるオオクニヌシが、異母兄弟たちに迫害され、命を狙われたため、黄泉の国へと下りました。スサノオの宮殿を訪ね、スセリ姫に恋をして結ばれますが、舅のスサノオは愛娘の婿が気に入らず、三つの試練を課します。
オオクニヌシは、スセリ姫の助けを得て三度の試練をくぐりぬけ、スサノオの宝を奪って、スセリ姫とともに黄泉の国を抜け出しますが、結局、スサノオは婿を認め、オオクニヌシはスサノオの力を借りて異母兄弟を討ち、出雲の王となるのです。
これに似た話は、ギリシャ・ローマ神話の中でも、かなり成立が新しいといわれるエロス(クピド)とプシュケの物語です。
ある国の王女プシュケは、人間でありながらあまりにも美しすぎて、愛の女神アプロディテ(ビーナス)に憎まれます。ところが、アプロディテの息子エロスは、プシュケに恋をし、母には秘密にしてひそかに結婚します。
プシュケは、夜だけしか訪れない夫の正体を知らず、怪物ではないかと疑い、夫が寝入ったすきに、蝋燭を灯してみますと、まぶしいばかりに美しい神だったのです。
しかし、蝋のしたたりで目覚めたエロスは、プシュケの疑いに怒り傷つき、母のもとで病に伏せってしまいます。
怒ったアプロディテは、息子の嫁に三つの試練を課しますが、プシュケはエロスの助けですべてを果たし、神体となって正式にエロスと結ばれるのです。
舅の婿いじめと姑の嫁いじめ。
三度の試練の内容はちがいますが、妻、あるいは夫の助けでそれをのりきり、めでたく結ばれるという流れは、類を見ないほどに似ています。
日本神話とギリシャ・ローマ神話の類似は、明治時代から気づかれていました。
とはいえ、西と東にあまりに遠いため、長い間、「神話というものはどこでも似たような形をとる」ということで、片づけられてきました。
ところが近年、「これほど似た形はめったにない」という認識が出てきたのです。
狭義のオルフェウス型神話、つまり「夫が冥界から妻をつれもどそうとして、見てはいけないという禁忌を破り失敗した」という話は、旧大陸では、日本神話とギリシャ・ローマ神話にしかないのだそうです。
やはりこれは伝搬を考えるべきだろというので、古代北方騎馬民族スキタイから朝鮮半島、そして日本列島へ、という説が唱えられています。
スキタイは、紀元前7世紀ころから黒海沿岸にあり、前4世紀に最盛期を迎え、現在の南ロシアあたりに割拠したイラン系遊牧民です。
墳墓から美々しい黄金の装飾品が多数発掘されていますが、この黄金文化は、同じくイラン系のサルマタイ、アランといった遊牧民に継承されて4世紀まで続き、次いで、西進した匈奴と推測される遊牧民・フン族に受け継がれたわけです。
とはいえ、スキタイ神話は、ギリシャのヘロドトスが書き残したわずかなものしか知られておらず、イラン系遊牧民の後裔といわれるオセット族の伝承などを、考察資料とするしかないわけでして、日本神話との構造的な類似は指摘されていますが、ギリシャ・ローマ神話ほど明確に、似たエピソードが確認できるわけではありません。
また朝鮮半島の神話も、文献資料として残されたものが、12世紀に編纂された「三国史記」、13世紀に編纂された「三国遺事」のみであり、8世紀初頭に成立した「古事記」「日本書紀」とはタイムラグがありすぎますし、これも、構造的な類似にとどまっているのです。
しかし、神話構造の伝搬とのみ考えるには、あまりにも細部まで、日本神話とギリシャ・ローマ神話の一部のエピソードは似すぎています。
たしかに、紀元前のはるかな古代から、神話の骨組みの伝搬はあっただろうとも推測できますが、もう少し、記紀の成立した8世紀に近い時代に、具体的な神話エピソードの伝搬が、あったのではないでしょうか。
つまり、西方ローマ帝国の領域から、ユーラシア北方騎馬民族の交易路を経て、朝鮮半島へたどり着いた神話エピソードは、日本列島にまで渡り、日本神話に取り込まれて記録されたと考えられるわけですが、伝搬の途中では、文書での記録が遅すぎたために消えてしまい、東西の端のみに共通の神話が残った、ということなのではないでしょうか。
そうだとするならば、それはだいたい、いつころの話なのでしょうか。
ここで浮かび上がってくるのが、4世紀から6世紀、三国時代の朝鮮半島、新羅に栄えた黄金文化です。
古代北方騎馬民族と朝鮮半島の関係を語るとき、通常重視されるのは、まずは高句麗であり、次には百済で、これまで新羅は、あまり注目されていませんでした。
といいますのも、高句麗、百済の支配層は、北方民族の扶余(ふよ)であったからです。
江上波夫氏の有名な「北方騎馬民族日本征服説」も、この扶余に注目したものでして、簡単にいってしまえば、「騎馬民族である扶余の一派が日本列島にも渡って支配者となった」というものでした。
しかし、扶余が騎馬民族、つまり遊牧民であったという点では、否定的な意見の方が多いですし、実際の出土遺物から見れば、扶余が支配者であった百済、高句麗よりも、文化的には南方的要素の方が強いと見られる新羅の方が、ストレートに北方騎馬民族の黄金文化を受け入れているのです。
これはいいかえれば、百済、高句麗の方が漢化の度合いが大きい、つまりは高度に発達した中華文明を受け入れる時期が早かった、ということではないでしょうか。
匈奴にしろ鮮卑にしろ、モンゴル高原にいた北方騎馬民族は、中華文明の領域に入ることによって、独自の文化を失い、漢族化されているのです。
そもそも、百済、高句麗の成立した領域には、紀元前2世紀の衛満朝鮮にはじまり、漢族の亡命政権や出先機関が存在し、漢族も多く居住していて、内部からの漢化もありました。それにくらべて新羅は、地理的な関係から、中華文明との接触が間接的であり、独自の文化を醸成する期間が長かったわけです。これは、中華文明の側からいえば、「未開であった」ということになるのですが。
三国時代・新羅の独自性に注目したのは、由水常雄氏です。
由水氏は、ガラス工芸史、東西美術交渉史の研究者で、古代史が専門ではありませんが、三国時代の朝鮮半島でローマン・グラスが出土するのは新羅のみ、であることに着目し、新羅古墳の出土物から、4世紀から6世紀の新羅は「ローマ文化王国」であった、という斬新な説を唱えています。
実際、ローマン・グラスに限らず、新羅古墳のきらびやかな出土物は異色で、中華文明の影響が強かった百済、高句麗とは、趣を異にしているのです。
4世紀から6世紀といえば、ローマ帝国は末期状態で、フン族の到来、ゲルマン民族の大移動が起こり、4世紀末には東西ローマ分裂、5世紀の終わりには西ローマ帝国の滅亡という激動期でした。
しかし、ローマ帝国の文化は広範囲に影響を与えていて、周辺民族の文化と融合しながら、いわばローマ文化圏を形作っていたのです。
たとえばローマン・グラス。
ガラスの起源は、メソポタミアといわれています。その製法の一部(鉛ガラス)は、かなり早くから中華文明圏に伝わり、戦国時代の中国で、すでにトンボ玉が製造されていました。
しかし、紀元前後にローマ帝国で生まれた「吹きガラス」の技法は革命的なもので、ガラス器の大量生産を可能にし、たちまち帝国支配下の各地に伝わったのです。
新羅古墳出土のローマン・グラスの多くは、後期のもので、地中海東岸、アンティオキアからアレッポ、シリアのシドンやティル、エジプトのカイロやカラニスで生産されたものではないか、と考えられています。
これらは、黒海西岸、北岸地方に多量に輸出され、交易ルートに乗って南ロシア一帯にひろがり、北方ステップ地帯の騎馬民族によって、東へと運ばれた形跡があるのです。
当時の華北は、鮮卑を中心とする北方騎馬民族の侵入で、混乱状態にありました。漢族政権はやがて中原を追われて南朝となり、華北は漢化された騎馬民族の支配を受けます。
当時、ユーラシア大陸北方に大きな気候の変動があったのでは、と推測されているのですが、東西で騎馬民族の大移動があり、西はローマ文明、東は中華文明が、大きな揺らぎを見せていたのです。
そんな中で、ステップ路の東西交易を担ったのは、大きく西に張り出したフン族とイラン系騎馬民族、そして中原に侵入しなかった東方騎馬民族であったと考えられます。
新羅古墳の出土物で、ローマ文化圏の影響を示すものは、もちろん、ローマン・グラスだけではありません。
純金の冠、指輪、イヤリング、あでやかな人面模様のトンボ玉など、あきらかに中華文明圏とはかけ離れた文物が多く出土するのですが、圧巻は、深紅のガーネットを象眼した精巧な黄金剣です。
ローマの技法・模様に加えて、ケルト文様を融合させたその黄金剣の意匠は、アーサー王伝説に登場する宝剣といわれても違和感のないもので、北方騎馬民族の黄金文化というよりも、もっと直接的に、ローマ帝国支配下のヨーロッパ文化を感じさせるのです。
さて、その黄金剣なのですが、いっしょに出土したものは、純金のイヤリングやバックル、そして馬具類など、西方の香り高いものばかりなのですが、翡翠の勾玉だけが異色です。
翡翠の勾玉は、他の新羅古墳からもかならずといっていいほど出土しているのですが、西方的な意匠の黄金の冠に美しい翠緑色の勾玉が多数飾られているものも多く、これは、この時代の新羅のみで見られる東西の美の融合です。
現代の韓国の歴史学は、他地域から半島への文化の伝来や影響を、認めない傾向があります。わけても日本列島からの伝来は、すべて否定することをよしとするようでして、これらの翡翠の勾玉も「新羅独自のもの」という学者が多いようです。
しかし、これが硬玉翡翠であることはたしからしく、だとすれば、日本列島の翡翠であると考えるのが常識的でしょう。
古代中華文明圏でもてはやされた翡翠は軟玉であり、硬玉ではありません。
硬玉は世界的にも珍しく、ミャンマーの奥地と新潟県糸魚川にしかありません。越の国(新潟県)から出雲に至る日本海沿岸では、縄文時代から、糸魚川産硬玉翡翠の勾玉が、生産、流通していたのです。
うろ覚えで恐縮ですが、実際、日本の学者の分析では、「新羅古墳出土の翡翠は糸魚川産のものと成分は同じ」という分析結果が出ていたはずです。
古代、列島の日本海沿岸と半島の新羅に、人的交流や交易があったと考えるのは、自然なことでしょう。
そうなのです。翡翠の勾玉が新羅にもたらされ、そして日本列島には、ローマン・グラスやトンボ玉、そして黄金の装飾品が、新羅から渡って来ました。
古墳時代の日本列島、ガラス器の出土品で、注目されるのは、奈良県橿原市の新沢千塚古墳(126号墳)出土のローマン・グラスです。
新沢千塚126号墳は、5世紀前半から6世紀前半にかけて形成された群集墳の一つなのですが、きらびやかな出土物で知られ、5世紀後半のものと推測されます。
出土物のうち、無色透明のカットグラスの碗と瑠璃色のガラス皿は、あきらかにローマン・グラスで、あでやかなトンボ玉も、その技法からして、ローマ帝国支配下のエジプトのものであると推測されます。さらに、指輪やイヤリング、ブレスレッド、冠の一部なども、新羅古墳出土物との類似を見せているのです。
5世紀後半の日本列島は、倭の五王の時代で、中国南朝への朝貢が知られ、百済との関係が深いのですが、この時代の百済は、高句麗に攻められて南下し、日本列島や新羅とつながりの深い半島南部に首都を移しています。
新沢千塚126号墳の出土物を、百済と結びつける説もあるのですが、これはおかしな話で、やはり新羅に注目すべきではないでしょうか。
倭の五王といえば、巨大な前方後円墳と結びつけて考えられていますが、そのうちの伝仁徳天皇陵からも、ローマン・グラスは出土しています。
明治5年、仁徳陵の前方部がくずれ、修理にともない、前方内部の記録が残されました。
このときの出土品の一部と見られる太刀や鏡が海外流出し、ボストン美術館に所蔵されていることから、近年、これは計画的な発掘、そして盗掘でもあったのではないか、といわれているのですが、それはさておき、このときの絵付き記録に、カットグラスの器が描かれ、それは、新沢千塚126号墳出土のものに酷似したローマン・グラスなのです。
伝仁徳天皇陵は、5世紀半ばのものと推定されていますが、この時代の日本列島の巨大前方後円墳の多くが、天皇陵とされているため、学術的な発掘調査はされていません。
とはいえ、たとえ発掘されたとしても、新羅王陵のようなきらびやかな出土物は、望めないでしょう。
天皇陵の多くは、平安時代後期あたりから明治初期までの長期間、盗掘にさらされました。
朝鮮半島と日本列島の王陵は、形態がちがいます。
新羅のような小型の王陵であれば、後世、埋もれて目立たなくなりますが、日本の巨大な前方後円墳が、盗掘をまぬがれようはずもなく、黄金の文物が出土する可能性は、ほとんどないといえるでしょう。
しかし、そのわずかな残物に、ローマン・グラスが含まれているのです。
ところで、話はもとにもどり、ギリシャ・ローマ神話と日本神話の類似のエピソードなのですが、これは大部分、出雲神話と呼ばれる部分に含まれています。
そして、この出雲神話に、新羅が登場するのです。
「古事記」にはなく、「日本書紀」の一書(あるふみ)に出てくる話なのですが、大蛇退治の主人公・スサノオが、天界から追放されて最初に降り立ったのは、新羅の国でした。しかし、「此の地は吾居らまく欲せじ」といって、出雲に渡ったというのです。
新羅と出雲といえば、記紀と同じく8世紀に編纂された「風土記」には、国引き神話が出てきます。
出雲の国があまりに小さいので、まずは新羅の国の一部をひっぱり、ついで北方の佐伎(さき)国、良波(よなみ)国、北陸の都都(つつ)の岬の一部をひっぱって、領土としたというのです。
出雲から越にいたる日本海沿岸と新羅。
これはそのまま、翡翠の勾玉が流通した海路と重なります。
記紀神話において、スサノオの娘・スセリ姫と結ばれたオオクニヌシは、高志(こし・越)の国のヌナカワ姫に妻問いし、スセリ姫は嫉妬します。
いうまでもなく、越の国は翡翠の産地ですが、古代、その翡翠のとれる川は、沼名川(ぬなかわ)と呼ばれていました。
万葉集に、以下の歌があります。
沼名川の底なる玉
求めて得し玉かも 拾ひて得し玉かも
惜しき 君が老ゆらく惜しも
ヌナカワ姫は、翡翠を産する川の女神であり、支配者の娘と理解できます。
一方、新羅の建国神話にも、倭人が登場します。
先に述べましたように、残念ながら文字記録として残された朝鮮半島の建国神話は、12世紀にまで下ります。
したがって、はるか後世の知識・価値観で整理されたものではあるのですが、半島古代三国のうち新羅の建国神話にのみ倭人がかかわっているということ自体は、古くからの伝承と考えて、まちがいないでしょう。
日本でいえば平安時代末期、12世紀に成立した「三国史記」によれば、新羅の伝説時代、第1代から第4代の王に仕えて活躍した重臣・瓠公は、「未だ其の族姓を詳(つまびら)かにせず。本、倭人。初め、瓠(ひさご)を以て腰に繋ぎ、海を渡って来る」ですし、その瓠公が最後に仕えた脱解王は、「本、多婆那(たばな)国の所生なり。其の国は倭国の東北、一千里にあり」なのです。
倭の国の東北にある多婆那国。日本海沿岸の但馬か丹後ではないかと考えられるのですが、その多婆那国の王妃が卵を産み、王はそれを嫌って捨てるように命じます。結局王妃は、卵と宝物を布で包んで箱に入れ、海に流しました。
その箱は最初、半島の金官国(金官加羅)に流れ着きますが、金官国の人はこれをとらず、さらに流れて、新羅の海岸に着きます。新羅の老婆が箱を開けると、卵はすでに孵って、男の子になっていました。
この子が脱解で、長じて2代王の婿となり、3代王の遺言で、王位につくのです。
娘婿になることで王位を継ぐところなど、出雲神話と共通していますし、古い伝承であることを裏付けているといえるでしょう。
朝鮮半島の新羅、伽羅。日本海をはさんで、出雲、丹後、越。
この一円に、おそらくは九州北部も加わり、古くから、日本海文化圏が形成されていたのではないでしょうか。半島に倭人が居住し、また列島にも半島からの渡来人があったことでしょう。
そんなつながりの中で、新羅に伝えられたローマ文化は、日本列島にも届いたのです。
新羅は、古代朝鮮半島三国の中で、もっとも遅くに律令制を受け入れました。つまり、もっとも漢化が遅かったわけなのですが、それだけに、異色の文化を育み、いったん漢化を受け入れると、国家として急速な発展を見せ、ついに半島を統一しました。
しかし、高句麗、百済の滅亡により、新羅は、直接中華文明圏と接することとなり、否応なく脅威にさらされます。
そして、漢化された騎馬民族が黄金文化を捨てたように、新羅もかつてのローマ文化を忘れていくのですが、しかし統一新羅は、交易国であり続けました。ステップ路の交易は衰えますが、今度は南海路に乗り出します。
それはさておき、4世紀から6世紀の朝鮮島と日本列島を考えるとき、どうしても、文字記録が残る中華文明圏との関係を中心に考えがちですし、漢化の速度を、そのまま文明化の速度と受け取りがちです。
たしかに、そういった側面はあるのですが、結果的に、漢化の早かった高句麗、百済が滅び、辺境で独自性を保ち得た新羅と日本が生き残ったわけでして、中華文明圏からの適度な隔たりの利点、というものもあるでしょう。
日本神話にうかがえる、ギリシャ・ローマ神話の影。
新羅の出土物に見る、ローマ文明圏の華麗な文物。
古代、極東に存在したローマは、遠い時の彼方から、歴史の中の文明と国家について、雄弁に語りかけてくれているかのようです。